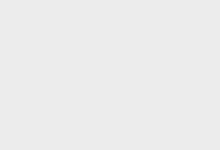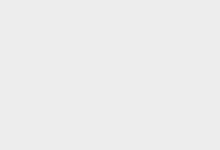春霞 ともに響きて 相まみえ ー 小味渕彦之(音楽評論家)
びわ湖ホールの大ホールや中ホールのロビーに立つと、有無を言わせずに飛び込んでくるのは、目前に広がる水面の風景だ。これは湖畔の芸術劇場ならではの特権。四季折々の変化にあわせて、その「あり様」は天候にも大きく左右される。
晴れた日には陽が煌き、浮き立つような光景が劇場に集う人々の心に寄り添う。
だがその一方で、荒天になればなるほどに容赦なく自然の激しさを見せつけられる。まさに同じ場所なのかというほどに、風景の表情が変わることになるのだ。台風襲来時の荒れ狂う雨風をロビーで目の当たりにすると、否が応でも恐ろしさを感じてしまうほどだ。
西洋において自然は対立するものであり、克服されるべき存在であり続けてきた。
西洋音楽の中でもその自然と対峙する精神は息づいている。人間が大きな存在である自然と向かい合うことこそが芸術の創造に結び付いていった。
一方日本では、自然は同化すべき存在であり、人の手の加わらないありのままの姿が尊重されてきた。「ゆく春を 近江の人と 惜しみける」という松尾芭蕉の俳句が、この音楽祭でも始められた時から掲げられている。春霞が立ち込めた琵琶湖の風景は、そこに集う人々と同化して渾然一体となるのだ。
人が集う意味を否が応でも考えさせられる昨今、われわれはどうしたら良いのかもわからずに、惑わされ続けてきた。
2021年の「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」は、「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」がテーマとなっている。ヴェルディのオペラ『ナブッコ』で歌われる有名な合唱曲からとられていて、祖国を思う捕虜たちの再興を願う歌だ。音楽祭では最終公演で、93歳の名匠、田中信昭がタクトを握ってびわ湖ホール声楽アンサンブルが歌う。惜しんでも惜しみきれないほど美しい春霞の中に、西洋の論理とは少し違うのかもしれないが、立ち上る音楽の響きに同化することを願いつつ足を運んでみたい。
われわれにとって自然も音楽も、共にあり続けるものであることを確かめるために。
小味渕彦之(音楽評論家)